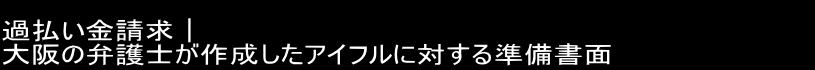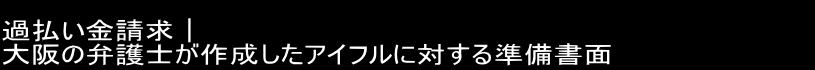「第4.返還すべき過払金は経済的合理性の観点より減額されること」について
ア 「1.主張の要旨」について
(ア) 被告アイフルの主張
「これまでの被告の主張に基づいて算出された過払金のうち、実際に原告に返還すべき金額は、以下に述べるとおり、経済的合理性の観点に基づいて過払金から45%相当分を減額した金額となる。」
(イ) 原告の認否及び反論
否認及び反論する。
被告アイフルの主張は,経済的合理性を根拠とするが,その経済的合理性がないばかりか,具体的な主張及び立証を欠くものであり,理由がない。
イ 「2.返還請求権の範囲について」について
(ア) 「 (1) 現存利益について」について
a 被告アイフルの主張
「被告は既に述べたとおり、悪意の受益者であることについては争うところであり、被告が善意の受益者であれば、本件不当利得返還請求において、現に利益の存する限度で利得を返還すれば足りる(民法703条)。
被告は原告を含め、顧客より受領した利息制限法超過利息の一部については既に法人税として納付しており、法人税として納付した部分に相当する範囲において被告において利益は現存していない。
従って、被告は、本件訴訟においても現に利益の存する限度である、原告より返済として受領した過払金のうち、既に法人税として納付した部分を除外した残余の部分について原告に返還すれば足りるものである。
原告からは、法人税の納付による金銭の消失は何ら被告が原告から得た不当利得とは関係ないとの反論が予想されるため以下に述べることとする。
ここで、いわゆる現存利益について念のため述べておくが、不当利得者のみならず、契約を取り消した未成年者(民法121条)や善意占有者(民法191条)などが物や金銭の返還義務を負うとき、取得したすべての利益を返還させることは酷なので、費消、滅失毀損損した分は差し引いて、現に利益を受ける限度で返還すればよいとされている。
たしかに、金銭の不当利得において利得が現存しないとされるためには、単に当該金員をもって他者に対する債務を弁済したり、必要な生活費を支弁したことだけでは足りない。
本件について、金銭の不当利得によって法人税を支払ったにもかかわらず、利益の現存が認められる場合を考察すると、利得者が損失者より得た利得によって、本来支払わなければならない法人税を納付した場合である。すなわち、被告は原告より得た利得によって法人税を支払うことにより、本来であれば当該法人税を支払うための他の支出を免れていたことになるのであるから、このような場合であれば、現存利益はあることとなる。
一方、ここで被告が指摘しているのは、利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得と法人税の納付による不当利得の喪失は密接不可分な関係であること,及び利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得及び法人税の納付による不当利得の喪失がなければ,被告が他の財産を消費したとはみることができないということである。
すなわち、被告は、原告を含む顧客から利息制限法超過利息の支払いがあれば、その得た利息を益金として法人税の税額を算出し国庫に納付することとなるが、利息制限法内の利息のみの支払であれば、当該超過部分だけ益金は減少することから、当然算出される法人税の税額も減少することとなり、被告は、利息制限法超過利息が原告を含む顧客から支払われたからこそ国庫に利息制限法超過利息を益金とする法人税を納付していたのであって、被告による利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得と法人税の納付による不当利得の喪失は密接不可分な関係にあったものである。そして、利息制限法内の利息の支払いのみであれば、被告において利息制限法超過利息を益金として法人税の税額を算出し国庫に納付すべき事情はないのであるから、利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得及び法人税の納付による不当利得の喪失がなければ、被告が他の財産を消費したとはみることができない。
したがって、被告が返還すべき過払金は、法人税として納付した限度において現存しないというべきである。
b 原告の認否及び反論
(a) 否認及び争う。
(b) 被告アイフルは,利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得に対して法人税を納付したことにより,現存利益が減少したことを理由としている。
(c) しかしながら,被告アイフルは,利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得に対して法人税を納付したのであれば,かかる不当利得の返還により,利益(益金)が減少したのであれば,それに応じて,更正決定を受けて払い過ぎた法人税の還付を受ければ良いのである。かかる議論を被告アイフルは見落としており,理由がない。
(d) そして,被告アイフルは,過払金の返還による損失の生ずる予測に対して,引当金を設定することができる。
ところで,引当金とは,「実際には未だ財貨又は役務の費消が確定しておらず(未費消),支払又は支払義務の確定がなされていなくても(未支出),適正な期間損益計算の見地から費用又は損失を見越し計上する場合に,借方に計上される費用又は損失に見合って借方に計上される項目」である。
現在,被告アイフルは,次のとおり引当金を設定しており,引当金設定に要する金額を損金計上している。これにより,租税上の効果(事実上の減税効果)を得ている。
被告アイフルは,平成20年4月1日~平成21年3月31日の事業年度において,「利息返還損失引当金繰入額」として,次のとおり計上している。
連結決算ベース 金583億1500万円
被告アイフル単独決算ベース 金398億7700万円
被告アイフルは,このように多額の利息返還損失引当金繰入額を,その他の営業費用として計上している(甲8号証,71頁,112頁)。
しかも,同事業年度の有価証券報告書の連結決算の部において,被告アイフルは,「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」「4.会計処理基準に関する事項」「(3) 重要な引当金の計上」において次のとおり述べている。
前連結会計年度の行
ニ 利息返還損失引当金
将来の利息返還金の発生に備えるため,過去の返還実績を踏まえ,かつ,最近の返還状況を考慮する等により,返還見込額を合理的に見積もり計上しております。
当連結会計年度
ニ 利息返還損失引当金
同左
(甲8号証,80頁)。
加えて,同事業年度の有価証券報告書の被告アイフル単独決算の部において,被告アイフルは,「重要な会計方針」「6.引当金の計上基準」において次のとおり述べている。
前事業年度の行
(4) 利息返還損失引当金
将来の利息返還金の発生に備えるため,過去の返還実績を踏まえ,かつ,最近の返還状況を考慮する等により,返還見込額を合理的に見積もり計上しております。
当事業年度
(4) 利息返還損失引当金
同左
(甲8号証,120頁)。
従って,被告アイフルは,自ら利息返還損失引当金を「将来の利息返還金の発生に備えるため,過去の返還実績を踏まえ,かつ,最近の返還状況を考慮する等により,返還見込額を合理的に見積もり計上して」いることを認めているのであるから,被告アイフルの主張に理由がないことは明らかである。
また,前述のとおり「利息返還損失引当繰入金」を計上しており,これにより,税効果を得ている。
仮に,本件における被告アイフルの主張が正当なのであれば,有価証券報告書には,虚偽の内容を記載したことを意味する。
それにもかかわらず,この租税上の効果について,被告アイフルは,何ら触れていない。被告アイフルの主張は,税効果会計に関し,独自の見解を述べるに過ぎず,理由がない。
なお,被告アイフルは,過去において,適正な引当金を設定しなかったというのであれば,それは,被告アイフル経営者の見越しの誤りに起因するものであって,過払金被害者である原告がそ被告アイフル経営者の見越しの誤りの責任を負うものではない。
(e) 加えて,被告アイフルは,各事業年度の所得に対しておよそ40%程度の法人税有効税率を乗じて算出されていることを公知の事実としているが,かかる事実は公知の事実とは言い難く,この点,強く争う。被告アイフルは,受領した利息制限法超過利息を益金として計上したことにより,実際に,どれだけの法人税等が賦課されたのかを主張・立証する必要があるにもかかわらず,これを怠っている。
従って,被告アイフルは,この点を具体的に主張・立証されたい。仮に,被告アイフルがこの点を具体的に主張・立証しないのであれば,かかる主張は,失敗したものとして扱われるものである。
(イ) 「 (2) 現存利益に関する判例について」について
a 被告アイフルの主張
「実際、不当利得において利益が現存しないと認められた判例には以下のような事例がある。
① 最高裁昭和50年6月27日第二小法廷判決
準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によって得た利益を賭博で浪費した事案において、『被上告人が本件金銭消費貸借契約に基づいて得た利益は、賭博に浪費されて現存しないものであるから、被上告人はその返還義務を負わないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。』として、契約を取消した行為無能力者に対する利得返還請求権に関する事例であるが、取消しうべき行為によって得た事実上の利益が、そのまま又は形を変えて残存しているときにかぎり、これを返還するを要し、またそれだけの返還だけで足り、受け取ったものを浪費したときは、利益は現存しなくてよいとされている。
② 名古屋地裁昭和60年11月15日判決
被告が第三者から取立てを依頼された手形を銀行(原告)に預け入れ、手形が不渡りになっているにもかかわらず、手形相当金額を普通預金口座から払戻しを受け、被告が払戻し後直ちに上記第三者に当該金員を交付した事例において、『被告は、原告から金1700万円の支払があれば右金員を(取立委任者)へ交付するが、本件本件手形が不渡りになれば(取立委任者)に交付する義務がないことを当然の前提として(取立委任者)から本件手形の取立に受任したものであることは明らかであり、被告は、金1700万円が原告から支払われたからこそ(取立委任者)へ交付したのであって、被告による右金員の取得と喪失は密接不可分な関係にあったものである。そして、右以外には、当時被告において(取立委任者)の支払をなすべき事情は、本件全証拠によっても認められないから、右1700万円の取得及び喪失がなければ、被告が他の財産を消費したとみることはできない。従って、被告が返還すべき利益は現存しないというべきであり、抗弁は理由である。そうであれば、原告の不当利得の請求も理由がない。』として、被告に返還すべき利益は現存しないことを認めたものである。
③ 高松高裁昭和45年4月24日第二民事部判決
旧軍人の遺族扶助料の支給裁定の取消処分に基づき、誤払いされた遺族扶助料について返還を求めたところ、既に、自己の生活費、学費等に費消していた事案において、『その金額は比較的少額であり、また、支給方法も一定額を継続的に支給するというものであるから、前期認定のごとき事情にあった被控訴人の当時の生活状態からすると、この程度および形による収入の増加については、一般低所得給料生活者の昇給の場合と同様、それに伴って応分の支出の増加が生じたに相違ないものと認められるとともに、かような収入の増加がなかったならば、それはそれで右のごとき余分の支出をしないで済ますこともできたはずであると推側されるのである。のみならず、かりに右扶助料が支給されたのちしばらくは、これによって喪失を免れた財産が一部残存していたとしても、被控訴人に対してその返還請求がなされたのは右扶助料の最終支払日からでもすでに約5年が経過したのちのことであるから、その問には、右残存利益も、本件扶助料の支給にもとづく収入の増加に応じて拡大された生活規模に見合う支出のためにことごとく費消されてしまったものと推認するのが相当であって、これらの点を総合して考えるならば、本件においては、被控訴人の得た利益は有形的に現存しないばかりではなく、それを得たことによって喪失を免れた財産もなく、その他これを得なかったならば他の財産を費消していたであろうと認められる事情もないというべきであり、したがって、被控訴人の受けた利益はすでに現存しないと認めるのが相当であるといわなければならない』として、不当利得によって収入が増加することに起因した支出の増加についても、利益の現存を否定した事例である。」
b 原告の認否及び反論
(a) 判例の存在については,争わないが,被告アイフルの主張に対しては,否認及び争う。
(b) 「① 最高裁昭和50年6月27日第二小法廷判決」について
本件は,準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によって得た利益を賭博で浪費した事案において、「被上告人が本件金銭消費貸借契約に基づいて得た利益は、賭博に浪費されて現存しないものであるから、被上告人はその返還義務を負わない」ことを認めた判決である。
被告アイフルは,本件と同様に賭博により浪費したというのであろうか。それとも,某信託銀行の支援のために要した金銭を浪費というのであろうか。本件と全く関係のない判決の引用でしかない。
(c) 「② 名古屋地裁昭和60年11月15日判決」について
被告が第三者から取立てを依頼された手形を銀行(原告)に預け入れ、手形が不渡りになっているにもかかわらず、手形相当金額を普通預金口座から払戻しを受け、被告が払戻し後直ちに上記第三者に当該金員を交付した事例において、「被告は、原告から金1700万円の支払があれば右金員を(取立委任者)へ交付するが、本件本件手形が不渡りになれば(取立委任者)に交付する義務がないことを当然の前提として(取立委任者)から本件手形の取立に受任した」旨の事実認定を行い,これを前提として,「被告は、金1700万円が原告から支払われたからこそ(取立委任者)へ交付したのであって、被告による右金員の取得と喪失は密接不可分な関係にあったものである。」と判断したものである。この判断を基に,「右以外には、当時被告において(取立委任者)の支払をなすべき事情は、本件全証拠によっても認められないから、右1700万円の取得及び喪失がなければ、被告が他の財産を消費したとみることはできない。従って、被告が返還すべき利益は現存しないというべきであり、抗弁は理由である。そうであれば、原告の不当利得の請求も理由がない。」として、被告に返還すべき利益は現存しないことを認めたものである。
従って,本判例が,手形の交付と現金の取得との関係で,現金を取得したのであれば,手形の交付によって,不当利得は存在しない旨を述べたものに過ぎないことは,明らかである。
よって,本件過払金返還請求とは,何ら関係のない判決であることは明らかであり,被告アイフルの主張には理由がない。
(d) 「③ 高松高裁昭和45年4月24日第二民事部判決」について
本判決は,旧軍人の遺族扶助料の支給裁定の取消処分に基づき、誤払いされた遺族扶助料について返還を求めたところ、既に、自己の生活費、学費等に費消していた事案において、被控訴人の当時の生活状態から,一般低所得給料生活者の昇給の場合と同様、収入の増加に伴って応分の支出の増加することを認め,かような収入の増加がなかったならば、それはそれで右のごとき余分の支出をしないで済ますこともできたはずであると推側されるとし,又,本件扶助料の支給にもとづく収入の増加に応じて拡大された生活規模に見合う支出のためにことごとく費消されてしまったものと推認されるとしたものである。この推認から,被控訴人の得た利益は有形的に現存しないばかりではなく、それを得たことによって喪失を免れた財産もなく、その他これを得なかったならば他の財産を費消していたであろうと認められる事情もないというべきであり、したがって、被控訴人の受けた利益はすでに現存しないと認めるのが相当であるとしたものである。
この判例を前提として,被告アイフルの利益の現存を否定するのであれば,被告アイフルの収入が低所得者と同様に遺族扶助料の場合と同様でなければならない。しかしながら,被告アイフルは,長年にわたって,多大な利益を上げており,その収入も低所得給料生活者同様のものということはできない。1998年頃,被告アイフルは,住友信託銀行の経営危機の際には,その救済に入ったといわれるほど,潤沢な資金を有していたのである(甲9号証)。
従って,本判例は,本件とは全く関係のない事例に対するものであって,これを根拠として,収入が増加することに起因した支出の増加について,利益の現存を否定する根拠とはならない。
よって,被告アイフルの主張には,理由がない。
(ウ) 「 (3) 運用利益について」について
a 被告アイフルの主張
「また、原告からは、仮に被告の主張が認められ、被告が善意の受益者であるとしても、最高裁昭和38年12月24日第三小法廷判決を根拠に、被告は原告から得た不当利得を運用することにより利益を得ているのであるから、運用利益も返還すべきであるとの主張が予想される。
しかしながら、上記判例は、甲会社の設立に際して財産引受が無効であったため、その引き受けた丙会社の乙銀行に対する手形金債務の弁済が無効とされた事案であるが、乙銀行が当該弁済金を受領してから返還するまでの間のこれを運用して得べかりし商事法定利率による利益の返還につき、『不当利得された財産について、受益者の行為が加わることによって得られた収益につき、その返還義務の有無ないしその範囲については争いのあるところであるが、この点については、社会観念上受益者の行為の介入がなくても不当利得された財産から損失者が当然取得したであろうと考えられる範囲においては、損失者の損失があるものと解すべきであり』と述べているとおり、実際に被告が過払金によっていかなる運用利益を上げたか否かではなく、あくまで損失者である原告について支払った過払金について当然収益を取得したと考えられるかどうか判断されなければならず、かつ、『したがって、それが現存するかぎり同条にいう『利益ノ存スル限度』に含まれるものであって、その返還を要するものと解するのが相当である』と述べているとおり、仮に当該過払金について原告が社会観念上被告の行為の介入がなくても不当利得された財産から当然取得した収益が考えられるとしても、すでに述べているとおり、被告においてすでに法人税の納付により、それが現存していないのであるから、やはり被告が返還すべき過払金は法人税として納付した限度において現存しないというべきである。」
b 原告の認否及び反論
否認及び争う。
被告アイフルは長々と判例を批判するが,そもそも当該判例自体が本件とはかけ離れたものである。
原告は,何ら商事法定利率に基づく運用益を主張して返還請求を求めていない。
従って,本件とは何ら関係のない判決を根拠とする被告アイフルの主張は,失当である。
ここでの被告アイフルの主張から,被告アイフルが各個別の事案に応じた答弁書を提出せず,全ての不当利得返還請求事件において,画一化された答弁書や準備書面が提出していると考えられる。
被告アイフルは,各事案を十分に吟味した上で,各個別の不当利得返還請求事件に対する答弁書や準備書面を提出して,真面目に訴訟を遂行されたい。
原告は,ここに苦言を呈するものである。
(エ) 「 (4) 小括」について
a 被告アイフルの主張
「以上述べたとおり、利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得と法人税の納付による不当利得の喪失は密接不可分な関係であること、利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得及び法人税の納付による不当利得の喪失がなければ、被告が他の財産を消費したとはみることができないことより、被告が返還すべき過払金は、法人税として納付した限度において現存しない。」
b 原告の認否及び反論
否認及び反論する。
各個別の論点については,既に論破したところである。
すなわち,利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得と法人税の納付による不当利得の喪失は,関係がない。
そもそも被告アイフルが過払金返還請求によって生じた損失を税務署に対して,更正請求しなかったこと,及び,被告アイフルが過払金返還請求によって生ずるであろう損金を見越して引当金を計上しなかったことによって,納付する必要のない法人税等を納付したに過ぎないのである。
従って,利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得と法人税の納付による不当利得の喪失とは,関係がない。
よって,被告アイフルの主張には,理由がない。
ウ 「3.原告の返還請求権の具体的な範囲について」について
(ア) 第1段落について
a 被告アイフルの主張
「上記2で述べたとおり、被告が返還すべき過払金は、法人税として納付した限度において現存しないところであるが、具体的に被告が取得した過払金のうちどれくらいの割合で法人税として納付されたことにより、利益が現存していないかについて、以下に述べるものとする。」
b 原告の認否及び反論
否認及び争う。
前述のとおり,被告アイフルが取得した過払金と法人税等の額とは,直接には関係のないものであり,被告アイフルが取得した過払金とこれにより払い過ぎた法人税等との関係を肯定する被告アイフルの主張は,理由がない。
(イ) 第2段落について
a 被告アイフルの主張
「被告会社は、日本国内に本店を有する法人であることから、これまで各事業年度において法人税の納税義務を負い、実際に納付を行ってきた。その納付額は、過払金返還請求が多数発生している、ここ数年の事業年度は除いて、その以前においては毎年450億円程度にのぼるものであり(周知の事実、被告アイフルホームページ参照)、各事業年度の所得に対しておよそ40%程度の法人税有効税率を乗じて算出されている(公知の事実)。」
b 原告の認否及び反論
否認及び争う。
確かに,各事業年度の所得に対して,およそ40%程度の法人税及び事業税が賦課されることはある。しかし,各事案にそれが当てはまるとは限らない。約40%の税率の中に被告アイフルが事業税を含めていないことからも,被告アイフル自身がこれを確認していないことの証左であり,その主張は理由がない。
従って,被告アイフルが周知の事実及び公知の事実としている事実は,周知及び公知の事実ではない。
被告アイフルは,これらの事実を周知及び公知の事実とするのであれば,これを立証されたい。
そもそも被告アイフルは,平成20年4月1日~平成21年3月31日の事業年度において,「利息返還損失引当金繰入額」として,金583億1500万円をその他の営業費用として計上しており,これによって税金の支払いを免れているのである(甲8号証,71頁)。
従って,被告アイフルの主張に理由がないことは明らかである。
(ウ) 第3段落乃至第10段落について
a 被告アイフルの主張
「しかしながら、既に述べているとおり、被告会社においては、貸金業法を遵守することにより利息制限法超過利率による貸金契約を消費者と締結し、利息制限法超過利息を受領することにより、その利息金を益金として各事業年度において所得の額を計上してきたところである。
すなわち、既に被告会社が支払った法人税には、利息制限法超過部分の利息が含まれていたものである。
概算ではあるが、過去の顧客との契約金利の平均値を28%とすると、そのうち利息制限法超過部分(金利18%~28%の部分すなわち10%相当部分)は、いわゆるグレーゾーン金利帯からの収入ということとなる。すなわち、被告会社における毎年の収入額のうち約35%(10%÷28%×100)はグレーゾーン金利帯に該当するのであるから、今になって、貸金業法43条のみなし弁済を否定するのであれば、当然、被告会社における毎年の収入額は約35%減少した金額だったことになる。
当然、収入が減少するのであれば、その収入を益金として算出し納付してきた法人税の金額は過大なものであったところであり、言うなれば、『税金の払い過ぎ』の状態だった。
仮に利息制限法超過部分の利息を含めた収入(益金)を100とすると、概ね損金は65、益金から損金を差引いた課税所得は35となり、毎年利息収入の35%が課税所得だった計算となる。
ここで、仮にグレーゾーン金利帯の収入がなかったとすると、収入は35%減少することになるから,収入(益金)は100から65に減少することとなり,損金65を差引くと,課税所得は0となる。
すなわち,被告会社において,仮に全ての取引についてみなし弁済を否定されると,法人税として納付すべきだった税金はほぼ0となる計算となり,支払った法人税は,全てグレーゾーン金利体帯からの収入すなわち利息制限法超過部分の利息金より支払ったこととなる。
実際に支払ってきた毎年の法人税額は、毎年受領してきた利息制限法超過部分の利息金額の約45%程度に相当することより、毎年受領してきた利息制限法超過部分の利息金のうち、その約45%については法人税の原資となっていた計算となる。言い換えれば、過払金の約45%は既に税金として支払っていて、被告の手元には残っていないこととなり、経済的合理性の観点から言えば、原告に対しては過払金の残余の部分、すなわち被告の手元に残っている過払金の55%相当の部分のみ支払えば足りる。」
b 原告の認否及び反論
(ア) 全て否認及び争う。
(b) そもそも被告アイフルは,平成20年4月1日~平成21年3月31日の事業年度において,「利息返還損失引当金繰入額」として,次のとおり計上している。
連結決算ベース 金583億1500万円
被告アイフル単独決算ベース 金398億7700万円
(c) 被告アイフルは,このように多額の利息返還損失引当金繰入額を,その他の営業費用として計上している(甲8号証,71頁,112頁)。
(d) しかも,同事業年度の有価証券報告書の連結決算の部において,被告アイフルは,「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」「4.会計処理基準に関する事項」「(3) 重要な引当金の計上」において次のとおり述べている。
前連結会計年度の行
ニ 利息返還損失引当金
将来の利息返還金の発生に備えるため,過去の返還実績を踏まえ,かつ,最近の返還状況を考慮する等により,返還見込額を合理的に見積もり計上しております。
当連結会計年度
ニ 利息返還損失引当金
同左
(甲8号証,80頁)。
(e) 加えて,同事業年度の有価証券報告書の被告アイフル単独決算の部において,被告アイフルは,「重要な会計方針」「6.引当金の計上基準」において次のとおり述べている。
前事業年度の行
(4) 利息返還損失引当金
将来の利息返還金の発生に備えるため,過去の返還実績を踏まえ,かつ,最近の返還状況を考慮する等により,返還見込額を合理的に見積もり計上しております。
当事業年度
(4) 利息返還損失引当金
同左
(甲8号証,120頁)。
従って,被告アイフルは,自ら利息返還損失引当金を「将来の利息返還金の発生に備えるため,過去の返還実績を踏まえ,かつ,最近の返還状況を考慮する等により,返還見込額を合理的に見積もり計上して」いることを認めているのであるから,被告アイフルの主張に理由がないことは明らかである。
仮に,本件における被告アイフルの主張が正当なのであれば,有価証券報告書には,虚偽の内容を記載したことを意味する。
エ 「4.結論」
(ア) 被告アイフルの主張
「したがって、実際に原告に返還すべき金額は、原告被告間の取引を利息制限法所定利率で再計算して算出された過払金のうち経済的合理性の観点に基づいて45%相当分を減額した金額、すなわち過払金の55%に相当する金額である。」
(イ) 原告の認否及び反論
否認及び争う。
被告アイフルの主張は,負債の部における「利息返還損失引当金」を計上し,また,損益計算書における「利息返還損失引当金繰入額」を計上することにより,税効果を得ていることを無視したのか,このような基本的な会計学上の知識を欠いた主張を論拠としており,理由のないことは明らかである。
よって,被告アイフルは,訴状記載の請求の趣旨どおりの過払金及びこれにより生じた利息を支払う義務がある。
ここは,目新しい論点のようなので徹底的に書きました。
ただ,よく見ると,アイフルの代理人は,自分の会社の損益計算書や貸借対照表も見ていないか,全く会計学的知識がないままに主張を展開していることが明らかです。
これは,ワザとでしょうか,それとも,もともと知らなかったのでしょうか。
大阪の弁護士を疑心暗鬼にさせる内容です。
|

サイト管理者
弁護士 佐 野 隆 久
南森町佐野法律特許事務所
電話 06-6136-1020
|